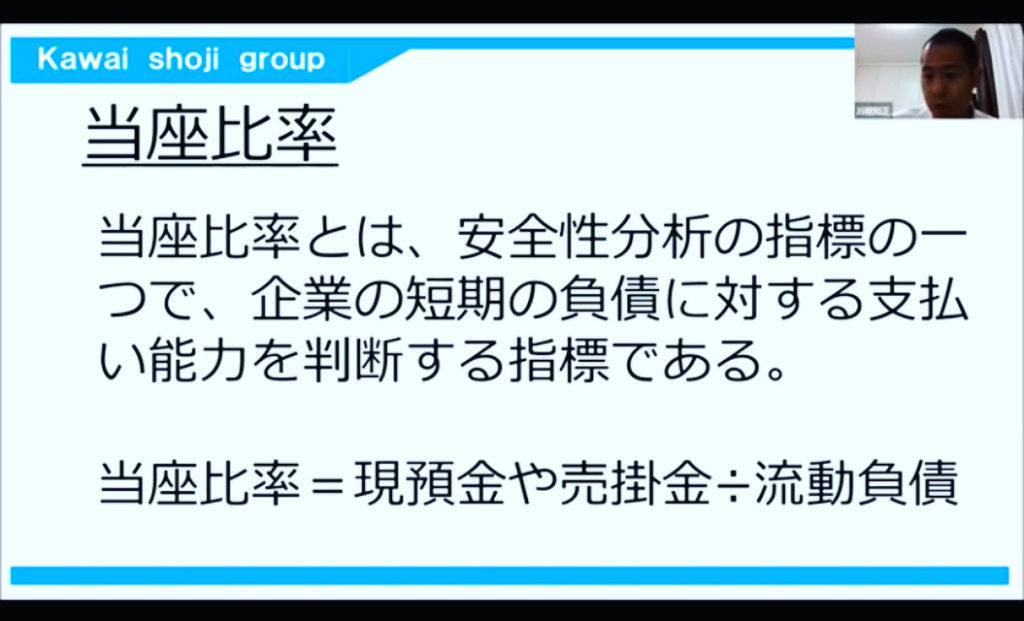会社で実施する社員旅行は無条件に福利厚生費として費用化出来る訳ではなく、要件から逸脱した場合には従業員への給与としてとり扱われる可能性もあります。国税庁のタックスアンサーによれば、旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められることに加えて、①旅行の期間が4泊5日以内であることと②旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であることを満たせば、原則として参加者の給与としなくて良いとされています。
ここで、タックスアンサーの参考事例で、4泊5日で参加率100%、使用者負担が1人当たり10万円の旅行については、「旅行期間・参加割合の要件及び少額不追求の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として課税しなくてもよい」とされているため、その他の旅行の条件も含めて総合的に勘案し判定する必要はありますが、その結果当該事例内であれば大丈夫かと考えられます。
一方で平成22年の公表裁決事例においては、1人当たり約24万円の2泊3日の旅行について、「少額不追求の観点から、強いて課税しないとして取り扱うべき根拠はない」として給与とされた事例もあります。
1人当たり10万円を超えると画一的に給与と取り扱う事になるわけではないですが、注意が必要です。